篳篥(ひちりき)の始め方|初心者でも雅楽の神秘的な音色を奏でる第一歩
※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「篳篥を始めてみたいけれど、何から手をつければいいのか分からない」
そう思って、なかなか最初の一歩が踏み出せずにいませんか?
雅楽の独特で神秘的な音色に魅せられつつも、その歴史ある楽器の奥深さに、尻込みしてしまう気持ち、とてもよく分かります。
でも、ご安心ください。
この記事を読めば、篳篥を始めるための具体的なステップが明確になり、安心して最初の一歩を踏み出せるはずです。
必要な道具の選び方から、音の出し方、練習のコツ、さらにはよくある疑問まで、初心者の方がスムーズに篳篥の世界に入れるよう、丁寧に解説していきます。
さあ、あなたも雅楽の美しい音色を奏でる喜びを体験してみませんか。
篳篥を始める魅力とは?

篳篥を始めることは、単に楽器を演奏する以上の豊かな体験をもたらします。
まず、その最大の魅力は、なんといっても篳篥が奏でる独特の音色にあります。
どこか懐かしく、そして神秘的なその音色は、聴く人の心に深く響き、非日常の世界へと誘ってくれるでしょう。
雅楽という日本の伝統芸能に触れることで、日本の歴史や文化を肌で感じられるのも、大きな喜びです。
また、篳篥の演奏は、集中力や精神力を高める効果も期待できます。
繊細な息遣いや指使いを習得する過程で、自分自身と向き合う時間が生まれ、日々の喧騒を忘れさせてくれるかもしれません。
最初は難しいと感じるかもしれませんが、少しずつ音が出せるようになり、やがて一曲通して演奏できた時の達成感は、何物にも代えがたいものです。
篳篥は、あなたの人生に新たな彩りと深い感動を与えてくれることでしょう。
【初心者向け】篳篥の始め方・ステップガイド

篳篥を始めるのは、決して難しいことではありません。
ここでは、初心者の方が安心してスタートできるよう、具体的なステップに分けて解説します。
ステップ1:篳篥の種類と選び方
篳篥には、主に「樹脂製」と「木製」があります。
樹脂製は比較的安価で、湿度による影響を受けにくく、手入れが簡単なため、初心者の方には特におすすめです。
木製は本格的な音色を楽しめますが、価格が高く、湿度管理など手入れに手間がかかります。
まずは樹脂製から始めて、慣れてきたら木製に移行するという選択肢も良いでしょう。
信頼できる楽器店や雅楽器専門店で相談し、実際に手に取ってみることをお勧めします。
ステップ2:蘆舌(ろぜつ)の選び方と調整
蘆舌は篳篥の「命」とも言える部分で、音色や吹きやすさを大きく左右します。
最初は既製品の蘆舌から始めるのが一般的です。
蘆舌は非常にデリケートなので、丁寧に扱う必要があります。
購入したら、まずは水に浸して十分に水分を含ませてから使用します。
吹きにくいと感じたら、少しずつ削って調整することもできますが、最初は専門家のアドバイスを受けるのが賢明です。
ステップ3:持ち方と構え方
篳篥は、両手でしっかりと持ち、口元にまっすぐ構えます。
姿勢は背筋を伸ばし、リラックスした状態を保つことが重要です。
指は、各孔をしっかりと塞げるように、自然なカーブを意識して置きます。
無理な力が入ると、音が出にくくなったり、疲労の原因になったりするので注意しましょう。
ステップ4:音の出し方(息の入れ方とアンブシュア)
篳篥の音を出すには、適切なアンブシュア(口の形)と息のコントロールが鍵となります。
蘆舌を唇で軽く挟み、口角を締めて、お腹からまっすぐ息を吹き込みます。
最初はなかなか音が出ないかもしれませんが、焦らず、様々な息の強さや口の形で試してみてください。
「ピー」というような甲高い音が出たら、それが第一歩です。
根気強く練習すれば、必ず美しい音色が出せるようになります。
ステップ5:指使いと運指
基本的な音が出せるようになったら、次は指使いを覚えましょう。
篳篥には、各孔を塞ぐことで異なる音を出すための運指表があります。
まずは、運指表を見ながら、ゆっくりと指を動かす練習から始めます。
最初は指が思うように動かないかもしれませんが、繰り返し練習することで、スムーズに運指できるようになります。
ステップ6:練習曲と練習方法
基本的な運指を覚えたら、簡単な練習曲に挑戦してみましょう。
雅楽の教則本には、初心者向けの簡単な曲が掲載されています。
毎日短時間でも良いので、継続して練習することが上達への近道です。
音源を聴きながら、リズムや音程を意識して練習すると、より効果的です。
ステップ7:メンテナンスと保管
篳篥は、演奏後に適切なお手入れをすることで、長く良い状態を保つことができます。
使用後は、露通しを使って管内の水分を拭き取り、蘆舌も水洗いして乾燥させます。
蘆舌は専用のケースに入れて保管し、篳篥本体は直射日光や高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管しましょう。
丁寧なメンテナンスが、美しい音色を保つ秘訣です。
篳篥を始めるのに必要なものリスト
篳篥を始めるにあたって、最低限揃えておきたい道具をリストアップしました。
これらを参考に、自分に合ったものを選んでみてください。
- 篳篥本体
- 初心者には樹脂製がおすすめです。価格も手頃で、手入れが楽なため、最初の一本として最適です。
- 蘆舌(ろぜつ)
- 篳篥の音色を左右する最も重要なパーツです。最初は既製品を数本用意し、自分に合うものを見つけるのが良いでしょう。予備も忘れずに。
- 蘆舌ケース
- デリケートな蘆舌を保護するために必須です。乾燥を防ぎ、破損から守ります。
- 露通し(つゆとおし)
- 演奏後に管内の水分を拭き取るための道具です。カビの発生を防ぎ、楽器を長持ちさせるために欠かせません。
- 教則本・運指表
- 基本的な吹き方や運指、簡単な練習曲が載っているものが良いでしょう。視覚的に理解できるDVD付きなどもおすすめです。
- 譜面台
- 姿勢を正しく保ちながら練習するためにあると便利です。
- チューナー(任意)
- 正確な音程で練習するために役立ちます。スマートフォンアプリでも代用可能です。
初心者が篳篥で失敗しないための注意点

篳篥を始めるにあたり、つまずきやすいポイントや、知っておくべき注意点をまとめました。
これらを事前に把握しておくことで、挫折することなく、楽しく練習を続けられるでしょう。
焦りは禁物!音が出なくても当たり前
篳篥は、他の管楽器と比べても音を出すのが難しいと言われています。
最初から美しい音色を期待せず、まずは「音を出す」ことを目標にしましょう。
数日、あるいは数週間かかっても音が出ないことは珍しくありません。
根気強く、毎日少しずつでも練習を続けることが大切です。
蘆舌の扱いは特にデリケートに
蘆舌は篳篥の最も繊細な部分です。
乾燥や衝撃に非常に弱いため、取り扱いには細心の注意を払ってください。
使用前には必ず水に浸し、使用後は丁寧に水洗いして乾燥させ、専用のケースに保管しましょう。
破損すると音が出なくなるだけでなく、修理や交換に費用がかかります。
独学の限界を知り、可能なら先生に習う
教則本や動画サイトで独学することも可能ですが、正しい吹き方や姿勢は、自己流では身につきにくいものです。
可能であれば、雅楽教室や個人レッスンで先生に直接指導を受けることを強くおすすめします。
プロの指導を受けることで、間違った癖がつくのを防ぎ、上達のスピードが格段に上がります。
練習場所の確保と周囲への配慮
篳篥の音は、想像以上に大きく響きます。
自宅で練習する際は、近隣への配慮が不可欠です。
防音対策を施したり、練習時間を工夫したり、カラオケボックスや貸しスタジオを利用するなど、周囲に迷惑がかからないように注意しましょう。
無理な練習は避ける
早く上達したい気持ちは分かりますが、無理な練習は唇や顎を痛める原因になります。
特に初心者のうちは、短時間でも毎日続けることを意識し、疲れたら休憩を挟むようにしましょう。
楽しみながら続けることが、上達への一番の秘訣です。
Q&A形式で初心者の疑問を解消!

篳篥を始めるにあたって、初心者の方が抱きがちな疑問をQ&A形式でまとめました。
あなたの不安や疑問を解消し、安心してスタートできるようサポートします。
- Q: 全くの初心者ですが、本当に音が出せるようになりますか?
- A: はい、もちろん音が出せるようになります。
篳篥は最初は音を出すのが難しい楽器ですが、正しい方法で根気強く練習すれば、誰でも美しい音色を奏でられるようになります。
焦らず、基本を大切に練習を続けてみてください。
- Q: 練習は毎日どれくらいの時間が必要ですか?
- A: 毎日15分から30分程度でも十分効果があります。
長時間練習するよりも、毎日継続して短時間でも触れることの方が上達には重要です。
無理のない範囲で、楽しみながら続けていきましょう。
- Q: 篳篥はどこで購入できますか?
- A: 雅楽器を専門に扱う楽器店や、オンラインストアで購入できます。
初心者の方は、樹脂製の篳篥から始めるのがおすすめです。
信頼できるお店を選び、店員さんに相談してみるのも良いでしょう。
- Q: 雅楽の知識が全くなくても始められますか?
- A: はい、全く問題ありません。
篳篥を演奏する中で、自然と雅楽の歴史や文化に触れることができます。
まずは楽器を楽しむことから始めて、興味が深まれば、さらに知識を広げていくのも良いでしょう。
- Q: 篳篥の音は大きいですか?近所迷惑にならないか心配です。
- A: 篳篥の音は、想像以上に響きます。
そのため、練習場所や時間帯には十分な配慮が必要です。
防音対策をしたり、練習スタジオを利用したり、周囲に迷惑がかからないよう工夫することが大切です。
まとめ:さあ、篳篥を始めよう!
この記事では、「篳篥を始めたいけれど、何から手をつければいいか分からない」というあなたの不安を解消し、最初の一歩を踏み出すための具体的なガイドを提供しました。
篳篥は、その独特の音色と奥深い歴史で、あなたの日常に新たな感動をもたらしてくれるでしょう。
必要な道具の選び方から、音の出し方、練習のコツ、そしてよくある疑問まで、初心者の方が安心して始められる情報を網羅しています。
最初は音を出すのが難しいと感じるかもしれませんが、焦らず、楽しみながら、毎日少しずつ練習を続けることが上達への鍵です。
この記事が、あなたが篳篥の世界へ踏み出すための確かな道しるべとなり、「読んでよかった」「動いてみようかな」と感じていただけたなら幸いです。
さあ、あなたも雅楽の神秘的な音色を奏でる素晴らしい体験を始めてみませんか。
きっと、新しい自分と出会えるはずです。





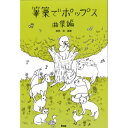


コメント