【初心者向け】笙の選び方完全ガイド!神秘の音色を奏でる最初の一歩
※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

笙を始めてみたいけれど、何から手をつければいいのか、不安に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。
雅楽の神秘的な音色に魅せられ、いつか自分も奏でてみたいと夢見ている方も多いのではないでしょうか。
しかし、笙は他の楽器と比べて情報が少なく、どこで手に入れればいいのか、どんな種類があるのか、選び方のポイントは何なのか、迷ってしまうのは当然のことです。
この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消し、笙選びの最初の一歩を自信を持って踏み出せるよう、徹底的にサポートします。
笙の魅力から、具体的な選び方、必要なもの、注意点まで、初心者の方が知りたい情報を網羅的に解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
この記事を読めば、あなたにぴったりの笙を見つけ、雅楽の世界への扉を開くことができるはずです。
さあ、一緒に笙の奥深い世界へ足を踏み入れてみましょう。
笙を始める魅力とは?

笙は、その神秘的で奥深い音色が特徴です。
雅楽の主要な楽器の一つであり、その音色は「天から差し込む光」に例えられるほど、荘厳で美しい響きを持っています。
笙を始めることは、単に楽器を演奏するだけでなく、日本の伝統文化に触れ、その歴史や精神性を深く理解することにも繋がります。
また、笙は「合竹(あいたけ)」と呼ばれる和音を奏でる楽器であり、複数の音を同時に出すことで、独特のハーモニーを生み出します。
この和音は、西洋音楽の和音とは異なる響きを持ち、演奏するたびに新たな発見と感動を与えてくれるでしょう。
さらに、笙の演奏は、集中力や精神の安定にも繋がると言われています。
ゆっくりと息を吹き込み、音を紡ぎ出す過程は、まるで瞑想のようであり、日々の喧騒を忘れさせてくれるひとときとなるでしょう。
笙を通じて、新しい自分を発見し、豊かな感性を育むことができるかもしれませんね。
この楽器が持つ唯一無二の魅力に触れてみませんか。
【初心者向け】笙の始め方・ステップガイド

笙を始めるにあたって、具体的なステップを知ることは非常に重要です。
ここでは、初心者の方がスムーズに笙の世界へ入っていけるよう、段階を追って解説していきます。
ステップ1:笙の種類を知り、自分に合ったものを選ぶ
笙には大きく分けて、伝統的な「本管(ほんかん)」と、比較的新しい「樹脂管(じゅしかん)」があります。
本管は竹で作られており、豊かな響きと深みのある音色が特徴ですが、湿気や温度変化に非常に敏感で、取り扱いには細心の注意が必要です。
価格も高価なものが多く、初心者には敷居が高いと感じるかもしれません。
一方、樹脂管は合成樹脂で作られており、湿気や温度変化に強く、メンテナンスが比較的容易です。
価格も本管に比べて手頃なものが多く、初心者の方には特におすすめです。
音色は本管に劣ると言われることもありますが、近年では品質が向上しており、十分な演奏が可能です。
まずは樹脂管から始めて、笙の扱いに慣れてから本管への移行を検討するのも良いでしょう。
ステップ2:笙を手に入れる場所を探す
笙は一般的な楽器店ではあまり取り扱っていません。
主に、雅楽器専門の店や、雅楽団体が運営する工房などで購入することができます。
インターネット通販でも見かけることがありますが、実物を見ずに高価な楽器を購入するのはリスクが高いため、可能であれば実店舗で試奏することをおすすめします。
中古品も選択肢の一つですが、笙は非常にデリケートな楽器なので、状態の悪いものを選んでしまうと後悔することになります。
信頼できる専門家に見てもらうか、専門店の保証があるものを選ぶようにしましょう。
レンタルサービスを提供している雅楽団体や教室もありますので、まずは試してみたいという方は、そういったサービスを利用してみてもいいかもしれません。
ステップ3:練習環境を整える
笙は、他の管楽器に比べて音量が小さいですが、それでも集合住宅などでは周囲への配慮が必要です。
練習場所を確保することが重要になります。
自宅で練習する場合は、防音対策を施すか、練習時間を工夫するなど、近隣住民への配慮を忘れないようにしましょう。
また、笙は湿気に弱いため、適切な湿度管理ができる場所で保管・練習することが非常に重要です。
乾燥剤や除湿器などを活用し、楽器が傷まないように注意を払ってください。
ステップ4:最初の音出しと基本的な指使いを学ぶ
笙の音出しは、他の管楽器とは少し異なります。
息を吸うときも吐くときも音が出るのが特徴で、これを「息継ぎ」と呼びます。
最初はなかなか音が出なかったり、不安定になったりするかもしれませんが、焦らずに繰り返し練習することが大切です。
基本的な指使いは、雅楽の教則本やオンラインの動画などで学ぶことができます。
まずは、単音を正確に出せるように練習し、次に「合竹」と呼ばれる和音に挑戦してみましょう。
指使いと息のコントロールを同時に行う必要があり、最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると徐々に美しいハーモニーを奏でられるようになります。
ステップ5:独学か教室か、自分に合った学習方法を選ぶ
笙の学習方法には、独学と教室に通う方法があります。
独学は、自分のペースで進められるというメリットがありますが、正しい奏法が身につかなかったり、疑問が解決できなかったりする可能性があります。
特に笙は、独学では難しい部分も多いため、挫折してしまうリスクも考えられます。
一方、雅楽教室に通うことは、専門家から直接指導を受けられるという大きなメリットがあります。
正しい奏法を身につけられるだけでなく、他の生徒さんとの交流を通じてモチベーションを維持しやすくなります。
また、雅楽の歴史や文化についても深く学ぶことができるでしょう。
まずは、体験レッスンに参加してみて、教室の雰囲気や先生との相性を確認してみるのがおすすめです。
自分に合った学習方法を見つけることが、笙を長く続けるための鍵となります。
笙を始めるのに必要なものリスト
笙を始めるにあたり、いくつか揃えておきたいものがあります。
ここでは、初心者の方が最低限必要となるものをリストアップしました。
- 笙本体:
前述の通り、初心者には樹脂管の笙がおすすめです。
価格帯は数万円から十数万円程度で、雅楽器専門店やオンラインストアで購入できます。
中古品を選ぶ場合は、状態をよく確認し、信頼できる販売元から購入するようにしましょう。
- 笙ケース:
笙は非常にデリケートな楽器なので、持ち運びや保管には専用のケースが必須です。
衝撃や湿気から楽器を守るためにも、しっかりとした作りのものを選びましょう。
多くの場合、笙本体とセットで販売されていますが、別売りの場合は楽器のサイズに合ったものを選んでください。
- 調律器(チューナー):
笙は、演奏前に調律が必要です。
特に初心者の方は、正確な音程を把握するためにも、チューナーがあると便利です。
スマートフォンのアプリでも代用できますが、専用のクリップ式チューナーの方が使いやすいかもしれません。
- 譜面台と楽譜:
練習する際には、楽譜を見ながら演奏することになります。
姿勢良く練習するためにも、安定した譜面台があると良いでしょう。
楽譜は、雅楽の教則本や、インターネットで公開されている無料の楽譜などを活用できます。
最初は簡単な曲から始めて、徐々に難しい曲に挑戦してみましょう。
- 防湿剤・乾燥剤:
笙は湿気に非常に弱いため、保管時には防湿対策が欠かせません。
ケースの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れておくことで、楽器を湿気から守ることができます。
定期的に交換するか、再生して使用できるタイプを選ぶと良いでしょう。
- お手入れ用品(柔らかい布など):
演奏後には、笙の表面や歌口(息を吹き込む部分)を柔らかい布で拭き、清潔に保つことが大切です。
特に歌口は、唾液などが付着するとカビの原因となることがあるため、こまめなお手入れを心がけましょう。
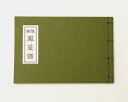
【 伊勢 宮忠 】【 譜本 笙 】幅19.3cm 厚さ1cm 高さ13cm 雅楽 雅楽器 和楽器 しょう 鳳笙譜 譜面 楽譜 総譜 スコア
価格:2750円 (2025/8/19時点)
楽天で詳細を見る
初心者が笙で失敗しないための注意点

笙は、その美しさとは裏腹に、非常にデリケートな楽器です。
初心者の方が失敗しないために、いくつかの重要な注意点があります。
1. 湿気と温度変化に細心の注意を払う
笙は、特に本管の場合、湿気と温度変化に極めて弱いです。
乾燥しすぎると割れてしまったり、湿気が多すぎるとリード(舌)が鳴らなくなったり、カビが生えたりすることがあります。
保管場所は、直射日光が当たらず、温度や湿度が安定した場所を選びましょう。
専用のケースに入れ、乾燥剤を定期的に交換することが必須です。
冬場など乾燥する時期は、加湿器を使うなどして、適切な湿度を保つよう心がけてください。
2. 無理な練習は避ける
笙の演奏は、肺活量や口の形(アンブシュア)が重要になります。
しかし、最初から長時間無理に練習すると、体調を崩したり、楽器を傷めたりする可能性があります。
特に、息を吸うときも音が出るという笙の特性上、めまいを感じることもあるかもしれません。
最初は短時間から始め、徐々に練習時間を増やしていくようにしましょう。
体調が悪いときは無理せず、休憩を挟むことも大切です。
3. 中古品や安価なものには慎重に
笙は高価な楽器ですが、だからといって安価な中古品に飛びつくのは危険です。
笙は繊細な調整が必要な楽器であり、状態の悪いものは修理に多額の費用がかかることがあります。
特に、リードの破損や管のひび割れなどは、素人目には分かりにくいものです。
もし中古品を検討する場合は、信頼できる雅楽器専門店で購入するか、専門家に見てもらうことを強くおすすめします。
初心者の方は、まずはメンテナンスが容易な樹脂管から始めるのが賢明な選択と言えるでしょう。
4. 独学の限界を知る
インターネットや教則本で独学することも可能ですが、笙は独学では習得が難しい楽器の一つです。
特に、正しい息の入れ方や指使い、音色のニュアンスなどは、実際に音を聞き、指導を受けることでしか身につかない部分が多くあります。
間違った癖がついてしまうと、後で直すのが非常に大変になることも。
可能であれば、雅楽教室や個人レッスンに通うことを検討してみましょう。
専門家からの指導は、上達への一番の近道となります。
5. 焦らず、長く続けることを目標に
笙の演奏は、一朝一夕で習得できるものではありません。
雅楽の奥深さに触れるには、継続的な努力と時間が必要です。
すぐに上達しなくても、焦らず自分のペースで楽しみながら続けていくことが最も重要です。
小さな進歩でも喜びを感じ、笙の音色に癒されながら、長く付き合っていくことを目標にしてみてください。
Q&A形式で初心者の疑問を解消!

笙を始めるにあたって、初心者の方が抱きがちな疑問をQ&A形式でまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
- Q: 笙はどこで買えますか?一般的な楽器店にはありますか?
- A: 笙は一般的な楽器店ではほとんど取り扱っていません。
主に、雅楽器専門の店や、雅楽団体が運営する工房で購入することができます。
インターネット通販でも見かけることがありますが、高価な買い物なので、可能であれば実物を見て試奏できる場所を選ぶことをおすすめします。
雅楽教室によっては、楽器の斡旋やレンタルを行っている場合もありますので、問い合わせてみてもいいかもしれませんね。
- Q: 練習場所はどこがいいですか?音は大きいですか?
- A: 笙の音量は、他の管楽器(例えばトランペットなど)に比べると比較的小さいです。
しかし、全く音がしないわけではないので、集合住宅などで練習する場合は、周囲への配慮が必要です。
自宅で練習する場合は、防音対策を施すか、練習時間を工夫するなど、近隣住民への配慮を忘れないようにしましょう。
カラオケボックスの個室や、貸しスタジオなどを利用する人もいます。
- Q: 独学でも笙は習得できますか?
- A: 独学で全く不可能というわけではありませんが、笙は非常に繊細な楽器であり、正しい奏法やメンテナンス方法を身につけるのが難しいです。
特に、息の入れ方や音色のニュアンスは、専門家から直接指導を受けるのが一番の近道です。
もし可能であれば、雅楽教室の体験レッスンに参加してみることを強くおすすめします。
独学で始める場合でも、オンラインの動画教材や教則本を複数活用すると良いでしょう。
- Q: 笙のメンテナンスは難しいですか?
- A: 笙は湿気に非常に弱いため、適切な湿度管理が最も重要です。
演奏後は、歌口を拭くなどの簡単な手入れは必要ですが、専門的なメンテナンスは専門家にお願いするのが一般的です。
特に本管の笙は、定期的な「焼き直し」という作業が必要になることがあり、これは素人にはできません。
樹脂管の笙は、本管に比べてメンテナンスが比較的容易なので、初心者には安心かもしれません。
- Q: 笙を始めるのにどれくらいの費用がかかりますか?
- A: 笙本体の価格は、種類や品質によって大きく異なります。
初心者向けの樹脂管であれば、数万円から十数万円程度で購入できるものが多いです。
本管の笙は、数十万円から数百万円と非常に高価になります。
その他、ケースや乾燥剤、教則本などの費用も考慮に入れる必要があります。
教室に通う場合は、月謝や入会金もかかりますが、専門的な指導を受けられるメリットを考えれば、価値のある投資と言えるでしょう。
まずは、レンタルサービスを利用して試してみるのも、費用を抑える良い方法です。
まとめ:さあ、笙を始めよう!
この記事では、笙を始めたいと考えている初心者の方に向けて、笙の魅力から具体的な選び方、必要なもの、そして失敗しないための注意点まで、幅広く解説してきました。
笙は、その神秘的な音色と奥深い歴史を持つ、非常に魅力的な楽器です。
最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、この記事で紹介したステップや注意点を参考にすれば、きっとあなたにぴったりの笙を見つけ、雅楽の世界への第一歩を踏み出せるはずです。
特に、初心者の方にはメンテナンスが比較的容易な樹脂管の笙から始めることを強くおすすめします。
また、独学も可能ですが、雅楽教室での専門的な指導は、上達への一番の近道となるでしょう。
笙の演奏は、心を落ち着かせ、豊かな感性を育む素晴らしい体験となるはずです。
この記事が、あなたの笙を始めるきっかけとなり、「読んでよかった」「よし、動いてみようかな」と感じていただけたら幸いです。
さあ、あなたも笙の美しい音色を奏で、新たな趣味の世界を広げてみませんか。
あなたの笙ライフが素晴らしいものになることを心から願っています。



コメント