防災グッズ、何から揃えればいい?初心者でも安心!本当に必要なものリストと始め方ガイド
※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「防災グッズを揃えなきゃ」
そう思ってはいるものの、何から手をつけていいか分からず、結局何もできていないという方は少なくないのではないでしょうか。
ニュースで災害の報道を見るたびに、漠然とした不安を感じるけれど、いざ準備となると、どこから始めればいいのか迷ってしまいますよね。
この記事は、そんなあなたの「始めたいけど何から始めればいいか分からない」という気持ちに寄り添い、最初の一歩を踏み出すための具体的な道しるべとなることを目指しています。
この記事を読めば、防災グッズの準備がぐっと身近に感じられ、安心して備えを進められるはずです。
「読んでよかった」「これなら動いてみようかな」そう思っていただけるように、分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。
防災グッズを揃える魅力とは?

防災グッズを揃えることは、単に物を準備するだけではありません。
それは、「もしも」の時に自分や大切な家族を守るための、具体的な行動です。
災害はいつ、どこで起こるか予測できませんが、備えがあることで心のゆとりが生まれます。
例えば、地震が起きた時、停電になった時、水が止まった時など、具体的な状況を想像してみてください。
必要なものが手元にあれば、パニックにならずに冷静に対処できる可能性が高まります。
また、防災グッズの準備は、家族とのコミュニケーションのきっかけにもなります。
「何が必要か」「どこに置くか」などを話し合うことで、家族全員が防災意識を高め、いざという時の役割分担も明確にできます。
この準備は、未来への投資とも言えるでしょう。
災害が起こらないことが一番ですが、万が一の時に「備えておいてよかった」と心から思える安心感は、何物にも代えがたい大きなメリットです。
今日から少しずつでも準備を始めることで、より安全で安心な毎日を送ることができるようになるでしょう。
【初心者向け】防災グッズの始め方・ステップガイド
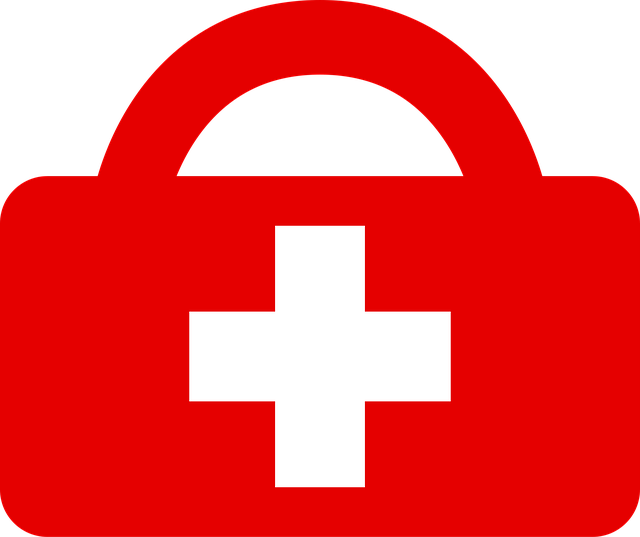
防災グッズの準備は、難しく考える必要はありません。
ここでは、誰でも簡単に始められるステップをご紹介します。
焦らず、一つずつ進めていきましょう。
ステップ1:まずは現状把握から始めよう
まずは、あなたの住んでいる地域の災害リスクを把握することから始めましょう。
自治体のハザードマップを確認し、地震、洪水、土砂災害など、どのような災害が起こりやすいのかを知ることが重要です。
これにより、必要な防災グッズの種類や量が変わってきます。
また、家族構成(乳幼児、高齢者、ペットの有無など)や持病の有無も考慮に入れましょう。
例えば、乳幼児がいる家庭では、粉ミルクやおむつ、離乳食なども追加で必要になります。
ステップ2:最低限必要なものをリストアップする
次に、「命を守る」ために最低限必要なものをリストアップします。
これは、避難時に持ち出す「非常持ち出し袋」に入れるものが中心となります。
水、食料(3日分が目安)、懐中電灯、ラジオ、常備薬、救急セットなどが挙げられます。
この段階では、完璧を目指す必要はありません。
まずは「これだけは!」というものをピックアップしてみましょう。
後ほど、具体的なリストを詳しくご紹介しますので、そちらも参考にしてみてください。
ステップ3:優先順位を決めて少しずつ揃える
リストアップしたものを一度に全て揃えるのは大変です。
まずは、優先順位の高いものから少しずつ購入していくのがおすすめです。
例えば、まずは水と食料、懐中電灯といった「生命維持」に関わるものから揃え始めると良いでしょう。
毎月の予算を決めて、少しずつ買い足していく方法も無理なく続けられるのでおすすめです。
「今月は水と非常食、来月はラジオと電池」といった具合に、計画的に進めてみてもいいかもしれません。
ステップ4:保管場所と管理方法を決める
防災グッズを揃えたら、どこに保管するかが重要です。
非常持ち出し袋は、玄関や寝室など、すぐに持ち出せる場所に置きましょう。
備蓄品は、食料庫や押し入れなど、家族全員が把握している場所にまとめて保管するのが理想です。
また、食料や水には賞味期限があるため、定期的なチェックと入れ替えが必要です。
年に一度、防災の日(9月1日)などに合わせて、家族で点検日を設けるのも良い習慣になります。
「ローリングストック法」といって、普段使いの食品を少し多めに買い置きし、使った分だけ買い足していく方法も非常におすすめです。
ステップ5:家族で防災について話し合う
最後に、家族全員で防災について話し合う時間を持ちましょう。
災害時の連絡方法、集合場所、避難経路などを事前に決めておくことで、いざという時にスムーズに行動できます。
子どもがいる場合は、防災グッズの中身を一緒に確認したり、避難訓練をしたりするのも良い経験になります。
家族みんなで防災意識を高めることが、最も強力な防災対策と言えるでしょう。
これらのステップを参考に、あなたとあなたの家族に合った防災準備を始めてみてください。
一歩ずつでも進めることが、安心への確実な道です。
防災グッズを始めるのに必要なものリスト
防災グッズは、大きく分けて「非常持ち出し袋」と「備蓄品」の2種類に分けられます。
ここでは、それぞれに必要なものを具体的にリストアップします。
1. 非常持ち出し袋(避難時にすぐに持ち出すもの)
災害発生直後、避難する際に持ち出すためのものです。
最低でも3日分、できれば1週間分を想定して準備しましょう。
- 水:1人1日3リットルを目安に、最低3日分。
- 非常食:乾パン、レトルト食品、栄養補助食品など、火を使わずに食べられるもの。
- 懐中電灯:予備の電池も忘れずに。ヘッドライトタイプも両手が空いて便利です。
- 携帯ラジオ:手回し充電式やソーラー充電式だと安心。
- モバイルバッテリー:スマートフォンなどの充電用。
- 救急セット:絆創膏、消毒液、包帯、常備薬、持病薬など。
- 防寒具:毛布、ブランケット、使い捨てカイロなど。
- 軍手・作業用手袋:ガラスの破片などから手を守る。
- ホイッスル:閉じ込められた際に居場所を知らせる。
- 現金:公衆電話や自動販売機などで必要になる場合がある。小銭も多めに。
- 貴重品:身分証明書、健康保険証のコピー、通帳のコピーなど。
- 着替え:下着、靴下など最低限のもの。
- 簡易トイレ:断水時に備えて。
- ウェットティッシュ・除菌シート:衛生管理に。
- ゴミ袋:様々な用途に使える。
- 筆記用具:メモや情報伝達に。
- 生理用品・おむつ:女性や乳幼児がいる場合。
2. 備蓄品(自宅で生活を維持するためのもの)
ライフラインが停止した場合に、自宅で数日間〜1週間程度生活するためのものです。
ローリングストック法を取り入れると、無理なく備蓄できます。
- 飲料水:1人1日3リットルを目安に、最低1週間分。
- 食料:レトルトご飯、缶詰、フリーズドライ食品、乾麺など、長期保存可能なもの。
- カセットコンロ・ガスボンベ:調理用。
- 簡易食器・ラップ:洗い物を減らすため。
- トイレットペーパー:多めに備蓄。
- ティッシュペーパー:多めに備蓄。
- ポリタンク:生活用水の確保用。
- 洗面用具:歯ブラシ、石鹸、シャンプーなど。
- 予備のメガネ・コンタクトレンズ:視力矯正が必要な場合。
- 常備薬:持病薬は多めに。
- 乾電池:様々な機器用。
- ビニールシート:雨漏り対策や防寒に。
- ガムテープ:補修や固定に。
- ハサミ・カッター:開封や切断に。
- ライター・マッチ:火の確保に。
これらのリストはあくまで基本的なものです。
ご自身のライフスタイルや家族構成に合わせて、必要なものを追加・調整してください。
例えば、ペットを飼っている場合は、ペットフードや水、常備薬なども忘れずに準備しましょう。

非常食セット 7日分 非常食 ごはん おかず スープ 12種42食セット 製造から5年保存 防災食 アルファ米 白米 保存食 防災 食品 備蓄 米 食料 レトルト食品 常温保存 長期保存食 備蓄食料 アイリスオーヤマ アイリスフーズ
価格:12800円 (2025/8/21時点)
楽天で詳細を見る

LEDヘッドライト USB充電式 USB-C 超高輝度 ヘッドランプ アウトドア用 ヘルメットライト 登山 キャンプ 散歩 作業用 工事 キャンプ 災害 停電用
価格:1890円 (2025/8/21時点)
楽天で詳細を見る

エレット ミニラジオライト(ET-18)コンパクト 懐中電灯 非常灯 防災 手のひらサイズ ポケットサイズ LEDライト 手回し式 ダイナモ充電 簡単操作 イエロー
価格:1540円 (2025/8/21時点)
楽天で詳細を見る

正規品★新作SNS話題★ モバイルバッテリー magsafe ワイヤレス 充電 20000mAh iPhone 軽量 小型 マグセーフ PD 22.5W高出力 18W高速蓄電 急速充電器 5台同時充電 ワイヤレス高出力 PD QC QI対応 残量目安デジタル表示 PSE認証
価格:2980円 (2025/8/21時点)
楽天で詳細を見る

非常用 トイレ袋 くるくるトイレ 10回分 【sanwa】 非常用トイレ 防災トイレ 簡易トイレ 携帯トイレ 災害用トイレ 防災グッズ 災害 防災 備蓄 使い切り 吸水シート 断水時 ジェル化 トイレ コンパクト
価格:2420円 (2025/8/21時点)
楽天で詳細を見る
初心者が防災グッズで失敗しないための注意点

防災グッズの準備は、ただ揃えれば良いというものではありません。
いくつかの注意点を知っておくことで、いざという時に「使えない」といった失敗を防ぐことができます。
1. 賞味期限・使用期限の確認を怠らない
非常食や飲料水、医薬品には必ず賞味期限や使用期限があります。
購入時に確認し、期限が近づいたら定期的に入れ替えを行いましょう。
「ローリングストック法」は、普段から消費しながら備蓄できるため、期限切れを防ぐのに非常に有効です。
年に一度、家族で点検日を決めるなど、習慣化することをおすすめします。
2. 電池切れ・故障に注意する
懐中電灯やラジオ、モバイルバッテリーなどは、いざという時に電池切れや故障で使えないという事態は避けたいものです。
定期的に動作確認を行い、電池は予備を多めに用意しておきましょう。
特に、充電式のものは、満充電の状態を保つように心がけてください。
手回し充電式やソーラー充電式のものも、電源が確保できない状況で非常に役立ちます。
3. 家族構成やライフスタイルに合わせる
防災グッズは、画一的なものではありません。
乳幼児、高齢者、持病のある方、ペットがいる家庭など、それぞれの状況に応じた準備が必要です。
例えば、アレルギーのある家族がいる場合は、アレルギー対応の非常食を選ぶ必要があります。
また、ペットのいる家庭では、ペット用の水やフード、リード、排泄用品なども忘れずに準備しましょう。
家族みんなで話し合い、個々のニーズに合わせたリストを作成することが大切です。
4. 重さや持ち出しやすさを考慮する
非常持ち出し袋は、いざという時にすぐに持ち出せる重さにすることが重要です。
あれもこれもと詰め込みすぎると、重すぎて持ち運べないという事態になりかねません。
大人一人で持ち運べる重さ(男性で15kg、女性で10kg程度が目安)を意識し、本当に必要なものだけを厳選しましょう。
また、リュックサックに入れる際は、重いものを下に入れるなど、バランスを考えて収納すると運びやすくなります。
5. 定期的な見直しと訓練を行う
一度揃えたら終わり、ではありません。
防災グッズは、定期的に見直し、必要に応じて更新することが大切です。
家族の成長やライフスタイルの変化に合わせて、中身を調整しましょう。
また、年に数回、実際に非常持ち出し袋を背負ってみる、避難経路を確認するといった簡単な訓練を行うことも有効です。
これにより、いざという時にスムーズに行動できるようになります。
これらの注意点を踏まえることで、より実用的な防災対策を進めることができるでしょう。
Q&A形式で初心者の疑問を解消!

防災グッズの準備に関して、初心者の方が抱きやすい疑問をQ&A形式でまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
- Q: 防災グッズはどこで買えますか?
- A: ホームセンターや家電量販店、ドラッグストア、100円ショップなどで手軽に購入できます。最近では、防災グッズの専門ショップやオンラインストアも充実しています。セット商品も販売されているので、まずはそこから始めてみてもいいかもしれません。
- Q: 防災グッズはどれくらいの頻度で見直すべきですか?
- A: 最低でも年に一度は中身を確認し、賞味期限や使用期限が切れていないか、電池が消耗していないかなどをチェックしましょう。防災の日(9月1日)や、年末の大掃除の時期など、定期的なタイミングを決めておくと忘れにくいです。
- Q: 非常持ち出し袋は家族の人数分必要ですか?
- A: 基本的には、一人一つ用意するのが理想です。特に、避難経路が分かれる可能性がある場合や、各自がすぐに持ち出せるようにするためです。ただし、小さなお子さんや高齢者など、自分で持ち運ぶのが難しい場合は、大人がまとめて持つことも考慮しましょう。
- Q: ペットを飼っている場合、何を準備すればいいですか?
- A: ペットフード(数日分)、水、常備薬、リード、排泄用品、ペットの情報を記した迷子札、写真などを準備しましょう。避難所によってはペットの受け入れが制限される場合もあるため、事前にペット同伴避難が可能な場所を確認しておくことも重要です。
- Q: 防災グッズ以外に、普段からできる防災対策はありますか?
- A: 家具の転倒防止対策、ガラス飛散防止フィルムの貼り付け、避難経路の確認、家族との連絡方法の共有などが挙げられます。また、地域の防災訓練に参加することも、非常に有効な対策です。日頃から防災意識を持つことが、何よりも大切です。
まとめ:さあ、防災グッズを始めよう!
この記事では、防災グッズの必要性から、具体的な始め方、必要なものリスト、そして失敗しないための注意点まで、初心者の方に向けて網羅的に解説してきました。
「防災」と聞くと、つい身構えてしまいがちですが、一つ一つのステップは決して難しいものではありません。
大切なのは、「何もしない」という選択をしないことです。
今日からできること、例えば「まずは水と懐中電灯だけ買ってみようかな」といった小さな一歩から始めてみてください。
備えがあることで、心のゆとりが生まれ、いざという時に冷静に行動できるようになります。
それは、あなた自身だけでなく、大切な家族を守ることにも繋がります。
この記事が、あなたの防災準備のきっかけとなり、「読んでよかった」「これなら動いてみようかな」と感じていただけたら幸いです。
さあ、今日からあなたも、安心できる未来のために、防災グッズの準備を始めてみましょう!
最終おすすめ商品:

1000円ポッキリ 送料無料 軽量コンパクト LEDヘッドライト SV-7329 ( LED 懐中電灯 アウトドア 省エネ エコ 停電 節電 震災 釣り 夜釣り 自転車 レジャー 作業 防災 登山 作業 災害 キャンプ ジョギング ランニング 散歩 ウォーキング 単四乾電池 )
価格:1000円 (2025/8/21時点)
楽天で詳細を見る
![★宅配便送料無料★【ライト 手回し 充電 防災用 ラジオ ラジオライト iPhone 手回し充電 懐中電灯 携帯充電 充電器 ランタン スマホ iPhone 防災 防災グッズ 地震対策 台風 災害】 [メール便不可] 手回し式充電ラジオ ミニライト](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/meets/cabinet/top/1007-77_r.jpg?_ex=128x128)
★宅配便送料無料★【ライト 手回し 充電 防災用 ラジオ ラジオライト iPhone 手回し充電 懐中電灯 携帯充電 充電器 ランタン スマホ iPhone 防災 防災グッズ 地震対策 台風 災害】 [メール便不可] 手回し式充電ラジオ ミニライト
価格:1980円 (2025/8/21時点)
楽天で詳細を見る







コメント