【初心者向け】篠笛の選び方ガイド!最初の1本で失敗しないための完全マニュアル
※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「篠笛を始めてみたいけど、何から手をつければいいのか分からない」
「たくさん種類があって、どれを選べばいいか迷ってしまう」
そんな風に感じていませんか?
日本の美しい音色を奏でる篠笛は、多くの人を魅了する素晴らしい楽器です。
しかし、いざ始めようとすると、その種類の多さや専門用語に戸惑い、最初の一歩がなかなか踏み出せないという方も少なくありません。
ご安心ください。
この記事では、そんなあなたの不安に寄り添い、篠笛選びの基本から、初心者でも失敗しないための具体的なポイントまで、徹底的に解説していきます。
これを読めば、あなたにぴったりの篠笛を見つけ、自信を持って篠笛の世界へ飛び込むことができるはずです。
さあ、一緒に篠笛の魅力的な世界への扉を開きましょう。
篠笛を始める魅力とは?

篠笛を始めることは、単に楽器を演奏する以上の豊かな体験をもたらしてくれます。
まず、その独特の音色は、日本の伝統的な風景や祭りの情景を思い起こさせ、聞く人の心を深く癒します。
自分自身でその音色を奏でられるようになる喜びは、何物にも代えがたい感動となるでしょう。
また、篠笛は比較的手軽に始められる和楽器の一つです。
ピアノやギターのように大きなスペースを必要とせず、持ち運びも簡単なので、どこでも気軽に練習できるのが魅力です。
日々の練習を通じて、集中力や表現力が自然と養われることも期待できます。
さらに、地域の祭りやイベントで演奏する機会に恵まれれば、新たな仲間との出会いや、地域文化への貢献といった喜びも得られるかもしれません。
篠笛は、あなたの生活に彩りと深みを与えてくれる、そんな素晴らしい趣味になることでしょう。
【初心者向け】篠笛の始め方・ステップガイド

篠笛を始めるのは、思っているよりもずっと簡単です。
ここでは、初心者の方がスムーズに篠笛の世界へ入っていけるよう、具体的なステップで解説します。
ステップ1:篠笛の種類を知り、最初の1本を選ぶ
篠笛には、主に「唄用(うたよう)」と「お囃子用(おはやしよう)」の2種類があります。
唄用篠笛は、西洋音階に合わせて調律されており、童謡や唱歌、現代曲などを演奏するのに適しています。
一方、お囃子用篠笛は、日本の伝統的な祭囃子や民謡を演奏するために作られており、独特の音階を持っています。
初心者の方には、まず唄用篠笛をおすすめします。
なぜなら、ドレミファソラシドの音階で演奏できるため、馴染みのある曲から始めやすいからです。
また、指孔の数も重要です。
一般的に、七孔(ななこう)または六孔(ろっこう)が主流ですが、初心者には七孔がおすすめです。
より多くの音が出せるため、演奏できる曲の幅が広がります。
調子(キー)については、八本調子(ハ長調に近い)が一般的で、多くの教本で採用されています。
まずはこのあたりから選んでみると良いでしょう。
ステップ2:篠笛を手に入れたら、まずは音を出してみよう
篠笛が手元に届いたら、いよいよ音出しです。
最初はなかなか音が出ないかもしれませんが、焦らず、リラックスして挑戦しましょう。
篠笛の歌口(息を吹き込む穴)に唇を軽く当て、「フー」と優しく息を吹き込みます。
口の形や息の角度を少しずつ変えながら、一番響きの良いポイントを探してみてください。
最初はかすれた音でも大丈夫です。
「ポー」という音が安定して出るようになったら、最初の成功です。
この音出しの練習は、篠笛演奏の最も基本的な部分であり、非常に重要です。
毎日少しずつでも続けることで、安定した音が出せるようになります。
ステップ3:基本的な指使いと楽譜に慣れる
音が出せるようになったら、次は指使いです。
篠笛の指孔をすべて閉じると、一番低い音が出ます。
そこから一つずつ指を離していくと、音が高くなっていきます。
教本には、基本的な指使いの図が必ず載っていますので、それを見ながら練習しましょう。
最初はゆっくりと、正確な指の動きを意識することが大切です。
楽譜に慣れることも重要ですが、篠笛の楽譜は数字譜(指孔の番号で音を示す)が使われることも多いので、五線譜が苦手な方でも安心です。
簡単な童謡など、知っている曲から挑戦してみると、モチベーションも維持しやすいでしょう。
ステップ4:練習を継続し、スキルアップを目指す
篠笛は、毎日の継続が上達への一番の近道です。
毎日長時間練習する必要はありません。
15分でも30分でも、毎日続けることが大切です。
音の強弱や、ビブラートなどの表現技法にも挑戦してみましょう。
もし可能であれば、篠笛教室に通ってみるのも良い選択です。
プロの指導を受けることで、独学では気づきにくい癖を直したり、より高度な技術を習得したりできます。
オンラインレッスンも増えているので、自宅で気軽に学ぶことも可能です。
篠笛は奥が深く、練習すればするほど新しい発見があります。
焦らず、自分のペースで楽しみながら続けていきましょう。
篠笛を始めるのに必要なものリスト
篠笛を始めるにあたって、最低限揃えておきたいものをリストアップしました。
これらを参考に、自分に合ったものを選んでみてください。
- 篠笛本体
- 唄用七孔八本調子が初心者には最もおすすめです。
- 素材は竹製が一般的ですが、プラスチック製や木製もあります。
竹製は音色が豊かですが、価格が高めで手入れも必要です。
プラスチック製は安価で手入れが楽ですが、音色は竹製に劣る場合があります。
- 篠笛袋
- 篠笛を傷や汚れから守るために必要です。
- 持ち運びにも便利で、様々なデザインがあります。
- 篠笛教本
- 基本的な吹き方や指使い、簡単な曲の楽譜が載っているものを選びましょう。
- CDやDVD付きのものが、音を確認しながら練習できるのでおすすめです。
- チューナー(音合わせ器)
- 正確な音程で演奏するために必須のアイテムです。
- スマートフォンアプリでも代用できます。
- 譜面台
- 楽譜を見ながら練習する際に、姿勢を保ちやすく、集中して練習できます。
- 折りたたみ式のコンパクトなものが便利です。
- お手入れ用品(クロスなど)
- 演奏後に篠笛の水分を拭き取ることで、カビやひび割れを防ぎ、長持ちさせることができます。
- 柔らかい布や専用のクリーニングロッドがあると良いでしょう。

譜面台 折りたたみ 読書台 筆記台 楽譜スタンド 三脚 スチール製 楽譜立て 楽譜置き 調節可能 練習用 発表会 演奏会 持ち運び便利 コンパクト 送料無料
価格:2600円 (2025/9/4時点)
楽天で詳細を見る
初心者が篠笛で失敗しないための注意点

篠笛を始めるにあたって、いくつかの注意点を知っておくことで、後悔のない選択ができます。
特に初心者の方が陥りやすい落とし穴を避けるために、以下のポイントを参考にしてください。
安すぎる篠笛には注意
インターネットなどで非常に安価な篠笛を見かけることがありますが、品質に問題がある場合があります。
音程が不安定だったり、材質が悪くすぐに壊れてしまったりすることも少なくありません。
せっかく始めたのに、楽器のせいで上達が妨げられるのはもったいないことです。
ある程度の品質が保証された、信頼できるメーカーや楽器店で購入することをおすすめします。
初心者向けのモデルでも、1万円前後から良いものが手に入ります。
いきなり高価なものを選ぶ必要はない
「どうせなら良いものを」と、最初から何万円もする高級な篠笛を選びたくなる気持ちもわかります。
しかし、初心者のうちは、自分の好みや演奏スタイルがまだ確立されていません。
高価な篠笛は、その分デリケートで手入れも難しく、かえって扱いにくいと感じるかもしれません。
まずは、手頃な価格帯で品質の良い入門用モデルから始めるのが賢明です。
上達していく中で、自分に本当に合った一本を見つける楽しみも増えるでしょう。
試奏の重要性
もし可能であれば、実際に楽器店で篠笛を試奏してみることを強くおすすめします。
同じ調子や指孔の数でも、個体差によって吹き心地や音色が変わることがあります。
自分の息の量や吹き方に合うか、実際に音を出してみて確認することが大切です。
店員さんに相談しながら、自分にぴったりの一本を見つけることができるかもしれません。
試奏が難しい場合は、レビュー評価の高いオンラインショップや、信頼できる工房から購入すると良いでしょう。
保管方法に気を配る
篠笛は竹や木でできているため、湿度や温度の変化に非常に敏感です。
直射日光の当たる場所や、エアコンの風が直接当たる場所に放置すると、ひび割れや変形の原因になります。
演奏後は、必ず水分を拭き取り、篠笛袋に入れて保管しましょう。
乾燥が気になる場合は、加湿器の近くに置くなどの工夫も必要かもしれません。
適切な手入れと保管で、大切な篠笛を長く愛用することができます。
Q&A形式で初心者の疑問を解消!
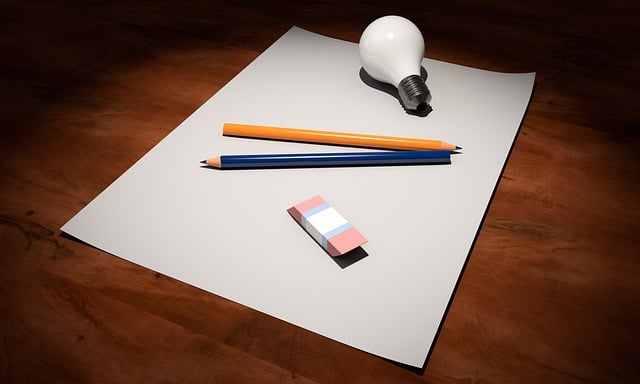
篠笛を始めるにあたって、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。
あなたの疑問もここで解決できるかもしれません。
- Q: 初心者におすすめの篠笛の調子(キー)はどれですか?
- A: 八本調子(はっぽんちょうし)が最もおすすめです。
これは西洋音階のハ長調に近い音階で、多くの教本や楽譜で採用されています。
馴染みのある曲を演奏しやすく、音域も広すぎず狭すぎず、バランスが良いため、最初の1本として最適です。
迷ったら八本調子を選んでみてもいいかもしれません。
- Q: 指孔の数は六孔と七孔、どちらが良いですか?
- A: 初心者には七孔(ななこう)をおすすめします。
七孔は、六孔よりも半音が出しやすく、演奏できる曲の幅が広がります。
特に唄用篠笛の場合、現代曲や唱歌を演奏する際に七孔の方が便利です。
六孔は伝統的なお囃子などで使われることが多いですが、まずは七孔で基本的な指使いに慣れるのが良いでしょう。
- Q: 篠笛の素材は何を選べば良いですか?
- A: 主に竹製、プラスチック製、木製があります。
竹製は最も伝統的で、豊かな響きと温かい音色が魅力ですが、価格が高めで手入れも必要です。
プラスチック製は安価で耐久性があり、手入れも簡単なので、「まずは気軽に始めてみたい」という方には良い選択肢です。
木製は竹製とプラスチック製の中間のような特性を持ちます。
予算や手入れの手間を考慮して選んでみてください。
- Q: 篠笛の音が出ません。どうすれば良いですか?
- A: 音が出ないのは、初心者によくある悩みです。
まずは、歌口(息を吹き込む穴)に唇をしっかり当て、息が漏れないように意識しましょう。
そして、息の角度と強さを少しずつ変えながら試してください。
口を「ウ」の形にして、細くまっすぐ息を吹き込むイメージです。
焦らず、リラックスして、「ポー」という音が安定して出るまで繰り返し練習することが大切です。
鏡を見ながら口の形を確認するのも効果的です。
- Q: 独学でも上達できますか?
- A: 独学でも上達は可能です。
最近では、YouTubeなどの動画サイトやオンラインレッスン、充実した教本がたくさんあります。
しかし、間違った癖がついてしまうと、後で直すのが大変になることもあります。
もし可能であれば、一度は篠笛教室の体験レッスンを受けてみることをおすすめします。
プロの指導を受けることで、効率的に正しい吹き方を身につけられるでしょう。
まとめ:さあ、篠笛を始めよう!
この記事では、篠笛を始めたいけれど何から手をつければいいか分からないというあなたの疑問や不安を解消するために、篠笛の選び方から始め方、注意点までを詳しく解説してきました。
篠笛は、その美しい音色と日本の伝統的な魅力で、あなたの生活に新たな彩りを与えてくれる素晴らしい楽器です。
「唄用七孔八本調子」の篠笛と教本があれば、今日からでも気軽に始めることができます。
最初は音が出なくても、指使いがぎこちなくても、焦らず、自分のペースで楽しみながら続けることが何よりも大切です。
もし迷ったら、この記事で紹介したポイントを思い出してみてください。
適切な篠笛を選び、正しい知識を持って一歩を踏み出せば、きっとあなたも素敵な篠笛ライフを送ることができるでしょう。
さあ、このガイドを読んで「読んでよかった、動いてみようかな」と感じたあなた。
日本の伝統楽器である篠笛の奥深い世界へ、ぜひ飛び込んでみてください。
きっと、かけがえのない感動と喜びがあなたを待っています。




コメント